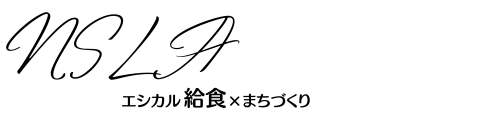PGSとは
Participatory Guarantee System
現在日本には有機農業を支える認証制度として国際有機農業運動連盟(IFOAM)の基準に則って作られたJAS認証制度があります。
これは第三者認証であり農水省の登録機関のみが認定できるしくみになっていますが、多額の費用や膨大な書類作成など、農家への負担が大きいこともあり小規模の生産者さんには有機JAS認証取得が難しいという現状があります。
一方、IFOAMにはもっと簡易な参加型の認証制度PGS[Participatory Guarantee Systems]があり、農家の負担を減らせるしくみが取られています。これは、国全体として認証を行うJASとは異なり、地域ごとに消費者、生産者が中心となって農場の調査や認証をしていく、というものです。



NSLAオーガニックJAPAN
NSLA Organic JAPAN
私たちナチュラルスクールランチアクションがエシカル給食普及をめざし、地産地消のオーガニック食材を給食に!と働きかけをするとき、頻繁に問題になるのは供給量や認証のこと。
日本の有機農地は農地全体の0.6%、そのうち有機JAS認証取得は約半分。残り半分の農地の生産物は、『有機』『オーガニック』としては流通できないので、学校給食に使うことは難しいのです。
こういった壁があることを知り、私たちは自分たちに何か出来ることはないのか探してきました。
どうしたら地元農家さんの野菜をオーガニック同等だと証明できるんだろう?
そこで、私たちが出会ったのがIFOAMが認定する地域参加型認証制度PGSです。
PGSは単に農産物の認証に留まらず地域づくり、社会づくりに繋がる素晴らしい理念があります。
私たちはこの取り組みに挑戦することで、給食へのオーガニック食材の提供だけではなく、子どもたちの未来のためのまちづくりに貢献できると考えています。
NPO法人NSLAは『NSLAオーガニックJAPAN』を活動グループ名とし、『IFOAM認定PGS』を目指して、現在ドイツのIFORMへ申請手続き中です。



NSLAオーガニックJAPAN PGSアドバイザー
私たちの挑戦を支えて下さっているPGSアドバイザーをご紹介します。
日本で唯一で世界で9番目のPGS認証団体『オーガニック雫石』でIFOAMとやり取りをされていたのが小宮さん。有機農業が分からない私たちへ丁寧にご指導いただき書類作成や提出の方法だけでなく悩み事までもサポートして頂いております。
小宮菱一
1967年早稲田大学理工学部電気通信学科卒業。工学博士。1998年以降マレーシアのマルチメディア大学、トゥンク・アブドゥル・ラマン大学に従事。 2008年に岩手県に移住。2013年から有機農業に取り組み、オーガニック雫石副代表となる。2016年にはIFOAM-Organics Internationalのメンバーに、2018年には日本で最初の(世界で9番目)IFOAM Recognized PGS Initiativesとなり、2021年からは、日本でPGSを取得したい団体で行う「連合PGS打ち合わせ会」を開催し、全国にオーガニックのFANを増やす活動のモデレーターとして活動中。